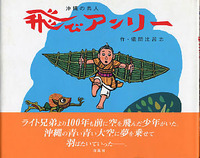2009年05月09日
飛び安里~その2~
「飛び安里」の復元モデル実寸大!があるということで
南風原町の大名鉄工にお伺いしました。

代表の島袋さんは飛び安里の復元だけでなく、
水陸両用の車いす「チェアボート」を発明したり、いろんなイベントで子どもたちに発明の楽しさを教えたりと様々な活動を行っている大変魅力的な方でした。
飛び安里の復元機は翼は横幅約8メートルもあります。
竹の骨組みと翼はパラグライダー用の生地を使っているとのこと。
翼の上部は南風原町特産の絣を使ってあってかわいいです。


この復元機、1999年に実際に飛行に成功した機体なんですよ。
当時の記事を沖縄タイムス紙面より
<1999年3月28日> 朝刊
「飛び安里」の羽ばたき機を再現しようと、「すきです南風原・夢・未来委員会」(島袋宗一会長)は二十七日、玉城村前川で復元機の初飛行に挑戦した。急斜面を駆け降りると機体はやや上昇し、地上約二メートル、距離にして五メートルほど飛んだ。滑空することはできなかったが、離陸には成功。メンバーからは大きな歓声が起こった。
島袋会長は「今日の様子を見て、必ず飛ぶと確信が持てた。機体バランスなどを調整し、再び挑戦したい」と話した。
当初、南風原町の黄金森公園でのフライトを予定していたが、風向きが悪く断念。移動した玉城村でも雨の土砂降りに、延期の可能性も出たが、天候は午後から次第に回復、風も向かい風に変わった。
乗り手を務めたのはスカイスポーツインストラクターの仲里裕和さん(44)。「バランスが取りづらく、滑空は難しかった」と感想を語り、「重心を見つけて修正すれば飛べるだろう」とアドバイスした。
* * *
この機体をもう一度組み立てて、夏休みに子どもたちにお披露目できるようにがんばります。
みなさん、ご協力よろしくお願いいたします!
南風原町の大名鉄工にお伺いしました。

代表の島袋さんは飛び安里の復元だけでなく、
水陸両用の車いす「チェアボート」を発明したり、いろんなイベントで子どもたちに発明の楽しさを教えたりと様々な活動を行っている大変魅力的な方でした。
飛び安里の復元機は翼は横幅約8メートルもあります。
竹の骨組みと翼はパラグライダー用の生地を使っているとのこと。
翼の上部は南風原町特産の絣を使ってあってかわいいです。


この復元機、1999年に実際に飛行に成功した機体なんですよ。
当時の記事を沖縄タイムス紙面より
<1999年3月28日> 朝刊
「飛び安里」の羽ばたき機を再現しようと、「すきです南風原・夢・未来委員会」(島袋宗一会長)は二十七日、玉城村前川で復元機の初飛行に挑戦した。急斜面を駆け降りると機体はやや上昇し、地上約二メートル、距離にして五メートルほど飛んだ。滑空することはできなかったが、離陸には成功。メンバーからは大きな歓声が起こった。
島袋会長は「今日の様子を見て、必ず飛ぶと確信が持てた。機体バランスなどを調整し、再び挑戦したい」と話した。
当初、南風原町の黄金森公園でのフライトを予定していたが、風向きが悪く断念。移動した玉城村でも雨の土砂降りに、延期の可能性も出たが、天候は午後から次第に回復、風も向かい風に変わった。
乗り手を務めたのはスカイスポーツインストラクターの仲里裕和さん(44)。「バランスが取りづらく、滑空は難しかった」と感想を語り、「重心を見つけて修正すれば飛べるだろう」とアドバイスした。
* * *
この機体をもう一度組み立てて、夏休みに子どもたちにお披露目できるようにがんばります。
みなさん、ご協力よろしくお願いいたします!
Posted by スタッフ03 at 11:14│Comments(1)
この記事へのコメント
200年前の「飛び安里の滑空機を復元して飛ばす」というプロジェクトには感動しました。
私はその新聞記事を読み、またテレビでも製作状況やテスト飛行の様子をかじりつくように見ていたのを思い出します。
機体もとても丁寧に作られ製作チームの意気込みを感じました。
しかし私は完成機を見てこれは飛ばないと思いました。
以下に私の個人的な見解を述べます。
まず飛行機(鳥も同じ)の翼は揚力を効率よく発生させるようにするために翼の上面はカーブしています。翼は前から風を受けると上下を流れる空気の速度の差によって揚力を発生させています。
今、速度を落とすために翼の迎え角を大きくしていくとあるところで空気が離れてしまい失速します。たとえ失速してもバランスを崩さずに回復できるようにするために翼の両はしに「翼端ねじり下げ」という角度をつけています。
これがないと失速した場合に横に突っ込んだりきりもみ状態になります。
飛び安里復元機にはこれがありませんでした。
確認方法は機体全体を前方から離れて見ると中心は太く端に行くに従って細くなるのが通常なのに対して復元機は逆に中心が細く、端に行くに従って太くなっている。
これはいえば翼端ねじり上げ(非常に危険な構造)の症状になっている。
テスト飛行をしたパイロットが「バランスが取りづらく、滑空は難しかった」と証言したことはまさにそのとおりであり、高所から飛行テストしなかったことだけが救いです。
重心を見つけて修正したとしても改善はされないとアドバイスしたいと思います。
以上が私の見解ですがこの場でこのような意見を述べることが場違いでしたら削除していただいて結構です。
ただ今後この機体でテスト飛行したいという話になった場合とても危険なので
やめていただきたいと思い投稿しました。
私はその新聞記事を読み、またテレビでも製作状況やテスト飛行の様子をかじりつくように見ていたのを思い出します。
機体もとても丁寧に作られ製作チームの意気込みを感じました。
しかし私は完成機を見てこれは飛ばないと思いました。
以下に私の個人的な見解を述べます。
まず飛行機(鳥も同じ)の翼は揚力を効率よく発生させるようにするために翼の上面はカーブしています。翼は前から風を受けると上下を流れる空気の速度の差によって揚力を発生させています。
今、速度を落とすために翼の迎え角を大きくしていくとあるところで空気が離れてしまい失速します。たとえ失速してもバランスを崩さずに回復できるようにするために翼の両はしに「翼端ねじり下げ」という角度をつけています。
これがないと失速した場合に横に突っ込んだりきりもみ状態になります。
飛び安里復元機にはこれがありませんでした。
確認方法は機体全体を前方から離れて見ると中心は太く端に行くに従って細くなるのが通常なのに対して復元機は逆に中心が細く、端に行くに従って太くなっている。
これはいえば翼端ねじり上げ(非常に危険な構造)の症状になっている。
テスト飛行をしたパイロットが「バランスが取りづらく、滑空は難しかった」と証言したことはまさにそのとおりであり、高所から飛行テストしなかったことだけが救いです。
重心を見つけて修正したとしても改善はされないとアドバイスしたいと思います。
以上が私の見解ですがこの場でこのような意見を述べることが場違いでしたら削除していただいて結構です。
ただ今後この機体でテスト飛行したいという話になった場合とても危険なので
やめていただきたいと思い投稿しました。
Posted by 空人 at 2009年06月26日 11:27